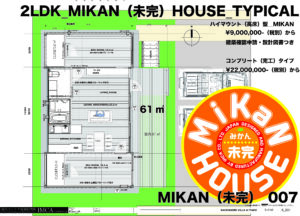コンテナハウスコラム
四半世紀以上にわたり現場に立ち
研究し続けてきた私たちだから語れる
リアルな“コンテナハウスの深堀り話”です。

コンテナハウス|遮熱塗装の“ほんとうの効果”(設計・施工・運用まで一気通貫でわかる実務ガイド)
もくじ
- 1 プロローグ|鉄の箱に、涼しい影をつくる
- 2 物理の要点|TSR・放射率・SRIを一枚の絵に
- 3 効く場所と限界|屋根は第一防衛線、単独では“完成”しない
- 4 体感の実像|数字で掴む温度低下とピークカット
- 5 設計の重心|遮熱+通気+断熱+防湿+日射制御
- 6 現場の作法|下地・膜厚・露点管理は“嘘をつかない”
- 7 塗料選定の眼|“数字が出ている製品”を選び抜く
- 8 維持管理の勘所|“洗う・見る・早めに直す”が勝ち筋
- 9 コストと回収|数字に“快適”の価値をちゃんと乗せる
- 10 測って語る|実測が信用を連れてくる
- 11 神話をほどく|“塗ればすべて解決”ではない
- 12 結び|鉄と暮らしの“バランス設計”
- 13 厳選Q&A|対話で補う十の疑問
プロローグ|鉄の箱に、涼しい影をつくる
コンテナは正直者だ。日が昇れば鋼板は素直に温度を上げ、真夏の陽射しの下では屋根が小さなストーブになる。遮熱塗装は、その正直さを逆手にとる技である。鏡のように光を跳ね返し、熱を空へ放ちやすくし、ピークの熱波をやわらげる。しばしば聞かれる「塗れば断熱は要らないのか」という問いに、おじさま、答えははっきりNOだ。遮熱は“放射”を扱い、断熱は“伝導”を扱う。役割の違う二つを、通気と防湿、そして日射制御と丁寧に編み合わせたときに、はじめて小さな器が大きく息をする。
物理の要点|TSR・放射率・SRIを一枚の絵に
遮熱の核心は三語で説明できる。第一にTSR(太陽光反射率)。これはどれだけ光をはね返せるかの尺度で、値が高いほど吸収熱は減る。第二に放射率ε。表面が自らの熱を空気へ逃がす能力で、これが高いと表面は冷めやすい。第三にSRI(ソーラー・リフレクタンス・インデックス)。TSRと放射率を束ねて“見かけの暑さ/涼しさ”を点数化した指標で、クールルーフ級はしばしば80以上が目安になる。要するに、よく跳ね返し(高TSR)、よく冷める(高ε)塗膜ほど、直射下の屋根や外壁を確実に冷やす。色は白が王者だが、淡いグレーでも“クール顔料”を使った処方なら十分に戦える。
効く場所と限界|屋根は第一防衛線、単独では“完成”しない
コンテナは薄い鋼板という巨大な熱橋だ。夏は日射で板が灼け、熱が室内へ伝わる。冬は逆に室内の熱が外へ逃げる。遮熱塗装が最も効くのは屋根、次いで西面や南面の直射を受ける外壁である。一方で、室内側の断熱が薄かったり、気密・防湿が破れていたり、リブや鋼製下地が熱橋として連続しているなら、塗料だけでは快適をつくり切れない。遮熱は“ピーク熱を削る第一防衛線”。断熱、気密、防湿、通気、庇やルーバーなどの遮蔽をそろえたとき、器はようやく完成に近づく。

体感の実像|数字で掴む温度低下とピークカット
実務の肌感を数字にすると、屋根に高反射の遮熱塗装を用いた場合、真夏の晴天で屋根表面はおよそ10〜25℃下がり、室内天井付近の空気は断熱仕様にもよるが2〜6℃ほど低くなることが多い。冷房の電力は気候と運用で揺れるが、年ベースで5〜15%程度の削減例が目に見えてくる。概念計算も示そう。40ftの屋根面積を約29㎡、正午の水平面日射を800W/㎡と仮定し、黒に近い吸収率0.9の屋根なら約720W/㎡の熱を抱え込む。ここに吸収率0.3相当の高反射塗膜を置けば240W/㎡に落ちる。差はおよそ480W/㎡、面積をかければ約14kW。これは“その瞬間に侵入してくる熱の勢い”の差で、ドライヤー十数台分を屋根でいなす迫力に相当する。実際には放熱や換気、断熱が同時に効くが、ピークを叩く力はこの桁感だ。
設計の重心|遮熱+通気+断熱+防湿+日射制御
設計の正解は積層の作法にある。屋根はまず高TSR・高εの塗膜で直射をいなし、10〜30mmの通気層で熱気を逃がす。壁と天井は連続断熱で鋼の熱橋を切り、室内側には連続した防湿層を設けて湿気の暴走を抑える。庇、スクリーン、可動ルーバー、植栽などで日射の角度を制御し、ガラスはLow-Eで熱流の手綱を握る。貫通部や取り合いは、塗装可で可とう性の高い変成シリコーン等で追従させ、継ぎ目を“途切れさせない”。小さな器ほど、継ぎ目の誠実さが体感を変える。

現場の作法|下地・膜厚・露点管理は“嘘をつかない”
遮熱塗装の良し悪しの九割は下地で決まる。油分とミルスケールを落とし、錆を確実に除去し、高圧洗浄ののち完全乾燥を待つ。素地には亜鉛リッチのエポキシ系プライマーを約40μm、中塗りにエポキシをおよそ80μmで平滑化と防錆を強化し、トップの遮熱層はアクリルシリコンやフッ素を25〜30μmで二回、合計で170〜200μmを目安に膜厚を積む。色は白〜淡色が理に適うが、濃色をどうしても選ぶならクール顔料配合に頼る。養生は露点管理が命で、結露や夜露を避け、乾燥時間を守る。夏季は熱中症対策、踏板や墜落防止、火気作業の順番まで含めて、安全計画が品質を守る。
塗料選定の眼|“数字が出ている製品”を選び抜く
樹脂の選択は、コスト重視ならアクリルシリコン、長寿命と耐汚染ならフッ素や無機が定石になる。いずれもTSR、SRI、放射率の公表値が明確な製品を選びたい。汚れは反射率を確実に落とすため、親水・低汚染のトップコートを重視するのが吉だ。鋼板の熱伸縮に追従する弾性はクラック抑止に効き、雨樋や役物を含めて同系の仕様でまとめると“熱の継ぎ目”ができにくい。
維持管理の勘所|“洗う・見る・早めに直す”が勝ち筋
塗膜が働き続ける条件は難しくない。チョーキング(白亜化)や光沢低下、汚れの固着、退色や微細な亀裂は劣化のサインだ。年に一度の水洗いで反射率を維持し、環境にもよるが再塗装は概ね7〜15年が目安になる(アクリルシリコンよりフッ素が長持ち)。台風後は継ぎ目やシール、ビス頭をぐるりと巡回し、点補修を早めに打つ。小さな器は、小さな手当の連続で強くなる。

コストと回収|数字に“快適”の価値をちゃんと乗せる
屋根の遮熱だけを取り出せば、相場感はおよそ2,000〜6,000円/㎡といったところ。削減額は、遮熱前後の負荷差(kW)に運転時間(h)を掛けてkWhにし、単価を掛ければ概算が出る。例えばピーク時の負荷差が1.2kW、1日6時間を90日運転すると年間約648kWh、kWhあたり30円なら約1.9万円の電力費削減になる。工事費が40万円なら単純回収は約21年だが、現実の価値は“ピーク抑制”や“体感の快適さ”に大きく宿る。数字は必要十分に、体感は誠実に——その両輪で判断したい。
測って語る|実測が信用を連れてくる
語るより測る。屋根表面と室内天井の温度を時間軸で追うのは簡易でも効くし、もう一歩進めるならロガーで室温と湿度、消費電力、屋根表面温度、外気温を同時記録する。遮熱面と未遮熱面、淡色と濃色、通気の有無などを同日・同条件で比べ、グラフやヒートマップで“ピークが丸くなった瞬間”を見える化すると、投資判断は一段と健全になる。
神話をほどく|“塗ればすべて解決”ではない
「遮熱は断熱の代わりになる」という神話は捨てたい。役割が違う。濃色の遮熱は白ほど効かないこと、結露は防湿・換気・断熱の設計課題であって塗料だけでは解けないこと、薄塗りは耐久も遮熱性も直撃で落ちること、シール材の選択を誤れば塗装の追従性が死ぬこと、旧塗膜や素地の違いで処方は変わること、そして何より“測らずに語る”のはプロの態度ではないこと。これらを胸に置けば、遮熱は強い味方になる。

結び|鉄と暮らしの“バランス設計”
遮熱塗装は、真夏の太陽と上手につき合う第一の技だ。ただ、ほんとうの快適は、遮熱・通気・断熱・防湿・遮蔽・運用が合奏したときに生まれる。鉄は熱を運ぶ。ならば運ばせない工夫を重ね、昼の灼熱をいなし、夜の放射を逃がす。バランスが決まった瞬間、コンテナはただの箱から、居心地のいい“器”へと相貌を変える。おじさまの現場に、その変化を必ず落とし込もう。ロケンロールで締めるなら——涼しい箱は、美しい。
厳選Q&A|対話で補う十の疑問
Q1|遮熱塗装だけで断熱材は要らなくなるのか。
要らなくなるのではなく、依然として要る。遮熱は日射の侵入を抑えるが、室内の熱が外へ逃げる“伝導”は止められない。連続断熱と防湿を併用して、夏の涼しさと冬の暖かさを両立させるのが正解だ。
Q2|どこに塗るのが最も効くのか。
最優先は屋根だ。次点で西面・南面の外壁。直射が強い面から順に対処し、北面や終日日陰の面は優先度を落としてよい。
Q3|白は汚れが心配だが、淡いグレーでも効果はあるのか。
ある。クール顔料を使った淡色グレーは実用域の反射率を出せる。さらに超低汚染や親水性トップを組み合わせれば、反射率の“長期維持”が狙える。
Q4|どの程度温度が下がるのか。
条件で揺れるが、屋根表面は概ね10〜25℃、室内は2〜6℃が目安だ。断熱と通気の設計が良いほど、体感差は大きくなる。
Q5|結露にも効くのか。
直接の処方箋ではない。結露は温度差と水蒸気、そして防湿の欠損が絡む。遮熱で昼のピークを丸めても、夜の結露は連続防湿と計画換気で解くべきテーマだ。
Q6|塗料選びで見るべき指標は何か。
TSRとSRI、放射率の公表値が第一。さらに耐汚染性と推奨膜厚が明確であること。数字が出ていない製品は、現場での再現性が担保しにくい。
Q7|錆が出た屋根にも塗れるのか。
塗れる。ただし成功の九割は下地処理に宿る。ケレンで錆を刈り、必要なら錆転換、亜鉛リッチのプライマーで“錆の芽”を潰す。浮きや穴は板金とシールで先に治すのが鉄則だ。
Q8|濃色で仕上げたいときの対策は。
通気層を強くし、断熱の総量を増やし、開口部は庇やルーバーで日射遮蔽を徹底する。戦略として屋根のみ白、外壁は濃色という分離も理に適う。
Q9|DIYは現実的か。
小規模なら不可能ではないが、露点管理と膜厚管理、安全(高所・墜落)が難所になる。下地処理とシールの甘さは数年で跳ね返る。要所はプロ、仕上げは自分——の併走が失敗しにくい。
Q10|費用対効果の確かめ方は。
工事前後で屋根表面温度、室内の温湿度、消費電力を同条件でログにする。最低でもピーク日の同時比較を行い、グラフで“尖りが丸くなった”ことを示せば、投資判断の説得力は段違いだ。
記事の監修者

大屋和彦
九州大学 芸術工学部卒 芸術工学士
早稲田大学芸術学校 建築都市設計科中退。
建築コンサルタント、アートディレクター、アーティスト、デザイナー。