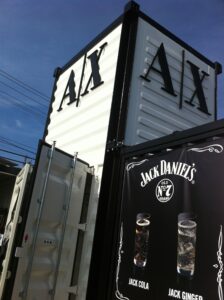コンテナハウスコラム
四半世紀以上にわたり現場に立ち
研究し続けてきた私たちだから語れる
リアルな“コンテナハウスの深堀り話”です。
更新日:2025.07.27
コンテナは地震に強い連載_他
コンテナハウスは地震に強いのか?_4/9(連載)

第3章:軽量で高剛性=「倒れにくさ」と「壊れにくさ」
耐震性能を考えるとき、建物の重さと構造の強さは、常に密接な関係にあります。
地震時、建物には横から大きな力(水平力)が加わります。
この力は建物の「質量」に比例して大きくなり、重い建物ほど揺れの影響を強く受けてしまいます。
これは地震力=建物重量 × 加速度というシンプルな数式でも示される、地震工学というかニュートン力学の基本法則です。
つまり──
「軽くて、しかも強い」建物こそ、地震に対してもっとも有利な構造だということ。
ここで、コンテナハウスが持つもう一つの特徴、「軽量×高剛性」という二律背反の性能が、地震に対する圧倒的な耐性として現れてきます。

もくじ
■ 軽いということは、「揺れにくい」ということ
木造住宅や鉄骨住宅と比べて、建築用新造コンテナは非常にコンパクトで、かつ軽量です。
標準的な20フィートのコンテナ1本で、およそ2.2〜2.5トン程度。建築用に強化されたものでも、1ユニットあたり3〜4トン程度の重量しかありません。
これを、同じ床面積の鉄筋コンクリート構造(RC造)と比較すると、コンテナの方が3分の1〜4分の1ほど軽量になります。
この“軽さ”が地震の初動において、「揺れの少なさ」=初動時の慣性力の低減につながるのです。
さらに、コンテナハウスは通常平屋または低層構造であり、重心が低いため倒れにくいというのも利点です。

■ でも「軽いだけ」なら、プレハブでも可能。でも違うんです。
軽量構造というだけなら、プレハブ住宅や仮設住宅にも同様のメリットがあります。
しかし、ここでの決定的な違いは、コンテナが“高剛性”であることです。
軽量であることと、強固であること。
この両立は本来、矛盾する性能です。
軽ければたわみやすく、強ければ重くなる──
このジレンマを、コンテナは『「鋼材の折り曲げ」と「面構造」による力の分散設計」』によって突破しています。

■ 高剛性=箱の「変形しにくさ」
建築用新造コンテナは、6面すべてが曲げ応力とせん断応力に強い鋼材パネルで構成されており、さらにリブ(補強の折り目)や内部フレームによって、一切の“たわみ”を許さない剛性を実現しています。
この構造は、たとえるなら「頑丈な金属の弁当箱」。中に荷物が入っていようがいまいが、『押しても引いても、びくともしない“芯の強さ”』があるのです。
地震で最も怖いのは、建物が「ねじれる」「曲がる」「バラける」こと。
コンテナのように変形しにくく、かつ全体で荷重を受ける構造は、これに対して非常に有効です。

■ 実は「変形しない=被害が少ない」
建物が一部でも変形すると、ドアが開かない、窓が割れる、壁がずれる、設備が外れる……という被害が連鎖的に広がります。
一方、構造体自体が変形しない(あるいは最小限)で済めば、生活インフラや家具・家財への被害も圧倒的に少ない。
この「生活被害の軽減」という視点でも、コンテナの高剛性は極めて有効です。
実際に震度5強〜6弱クラスの地震に見舞われたコンテナハウスでは、サッシがずれることもなく、内部の棚や冷蔵庫が倒れなかったというケースが多数報告されています。

■ 基礎構造との“タッグ”で最強に
加えて、コンテナの「軽量×高剛性」性能は、適切な基礎構造と組み合わせることで、さらに強力な耐震性を発揮します。
独立基礎を用いて、地震力を点で分散させる
ベタ基礎や布基礎によって、全体を面で支える
アンカー固定で、揺れのエネルギーを基礎に逃がす
このように、コンテナ+基礎の“二重構造”によって、倒れにくく・壊れにくい家が完成するのです。

■ 結論:「しなやかに、芯がある」強さがここにある
軽くて、でも強い。
硬くて、でもコンパクト。
変形しにくいけれど、倒れない。
そんな矛盾をすべて内包しているのが、建築用新造コンテナなのです。
コンテナハウスは、単なる“箱”ではありません。
それは揺れを受け止め、変形を許さず、暮らしを守る鋼鉄のシェルターなのです。
記事の監修者

大屋和彦
九州大学 芸術工学部卒 芸術工学士
早稲田大学芸術学校 建築都市設計科中退。
建築コンサルタント、アートディレクター、アーティスト、デザイナー。