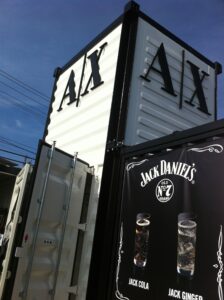コンテナハウスコラム
四半世紀以上にわたり現場に立ち
研究し続けてきた私たちだから語れる
リアルな“コンテナハウスの深堀り話”です。
更新日:2025.07.27
コンテナは地震に強い連載_他
コンテナハウスは地震に強いのか?_2/9(連載)

第1章:そもそもコンテナは「地震に強い構造」なのか?
「なぜコンテナは地震に強いのか?」
この問いに対する答えは、実は建築の領域を超えて、“力の構造”そのものにまで迫る話になります。
私たちが日常的に接する建物は、木造や鉄骨造、あるいは鉄筋コンクリート造といった構造形式を持っています。それらは基本的に柱と梁による“骨組み”構造で成り立っています。つまり、建物は“骨”のようなフレームで形を保ち、外装材や内装材がその外皮をつくる。
これに対して、コンテナハウスは根本的に構造の発想が違うのです。
もくじ
■ モノコック構造──自動車や飛行機が採用する“剛の箱”
建築用新造コンテナの構造は、いわゆるモノコック(Monocoque)構造にもなっているのです。
これは、“外皮そのものが構造体”となって力を受ける設計思想であり、地震のような横方向の力(水平力)やねじれに対して、構造全体で応答することができます。
例えるなら、在来木造住宅が「ティンバーフレームのテント」だとしたら、モノコック構造は「戦車のような鋼鉄の箱」。この“箱そのものが構造”という考え方こそが、コンテナを地震に強くする核心的なポイントなのです。
ただしこの事は事実でありながら、「構造計算上」は以下の構造的特質しかカウントしていません。上記は建築の構造計算上はプラス部分に入れていないのですが、事実コンテナを強固にしている特質なのです。

■ 四隅の「コーナーポスト」がすべてを支える
建築用新造コンテナの設計は、ISO国際規格の流れをくみながらも、建築法規に即して強度を再設計された構造体です。特徴的なのは、上下左右すべてのパネルが溶接され、一点の継ぎ目もなく一体化された剛体であること。その構造の要となるのが、四隅の「コーナーポスト」と呼ばれる鋼柱です。この4本のポストが、コンテナ全体の荷重・応力・揺れ・捻れを吸収し、さらに上下の連結・基礎への固定・積載時の積重ねすべてに対応する万能の柱となっています。
通常の建築であれば、地震の力が柱や梁、接合部に集中しやすくなりますが、コンテナ構造では力が“面”と“角”に分散されていくため、どの方向からの揺れにも比較的均等に耐えることができます。

■ 水平力への耐性がすごい
地震時、建物にかかる力の大半は、横からの揺れ=水平力です。
日本建築基準法でも、地震力は建物の重量に比例して加わる「水平加速度荷重」として設計時に想定されます。この水平力に対して、構造全体で受け止め、変形や倒壊を起こさないことが耐震設計の基本です。コンテナのような箱型構造は、面全体で横揺れを受け止める力学的に理想的な形なのです。
また、コンテナ自体が変形に強く、かつ短いスパンで剛性を保つため、地震時に生じる“固有周期”が小さく、共振による増幅を起こしにくいという特徴もあります。

■ 「建築用新造」であることの決定的な差
ここでひとつ重要な注意点があります。
巷で流通している「中古の海上コンテナ」は、確かにモノコック構造ではありますが、あくまで『物流用途に特化した“輸送器具”』であり、建築物としての設計基準や性能検査を満たしていません。また、海水による腐食、金属疲労、微細な歪みが蓄積された中古コンテナを使用した場合、“構造としての強さ”は保証されないどころか、逆にリスク要因となることもあります。
これに対し、私たちが扱うのは「建築用新造コンテナ」。建築基準法に基づき、材質・板厚・補強リブ・接合部の仕様など、すべてが“家を建てるため”にゼロから設計された構造体です。
つまり、地震に対する「真の強さ」とは、“どんな形をしているか”ではなく、“どのように設計されているか”で決まるのです。

■ まとめ:コンテナハウスの強さは、「構造」そのものに宿る
ここまで見てきたように、コンテナハウスの“地震に対する強さ”は、見た目やサイズの問題ではなく、構造そのものの本質にあります。
モノコック構造、コーナーポスト、全体剛性、短スパン、面剛性、構造一体化……。これらの特徴は、すべて地震という“水平力の試練”に耐えるための理にかなった回答です。
“地震に強い建築”をゼロから再発明するとしたら、それはたぶん、コンテナハウスのような構造に行き着くはずです。
次章では、この構造に不可欠な「溶接剛接合」の技術的特性に迫ります。

記事の監修者

大屋和彦
九州大学 芸術工学部卒 芸術工学士
早稲田大学芸術学校 建築都市設計科中退。
建築コンサルタント、アートディレクター、アーティスト、デザイナー。