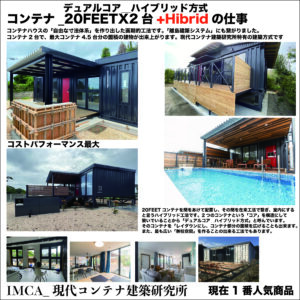コンテナハウスコラム
四半世紀以上にわたり現場に立ち
研究し続けてきた私たちだから語れる
リアルな“コンテナハウスの深堀り話”です。
更新日:2025.08.25
コンテナハウスと面積・台数
コンテナハウス_面積-5坪から20坪までの暮らしと可能性(10坪編)
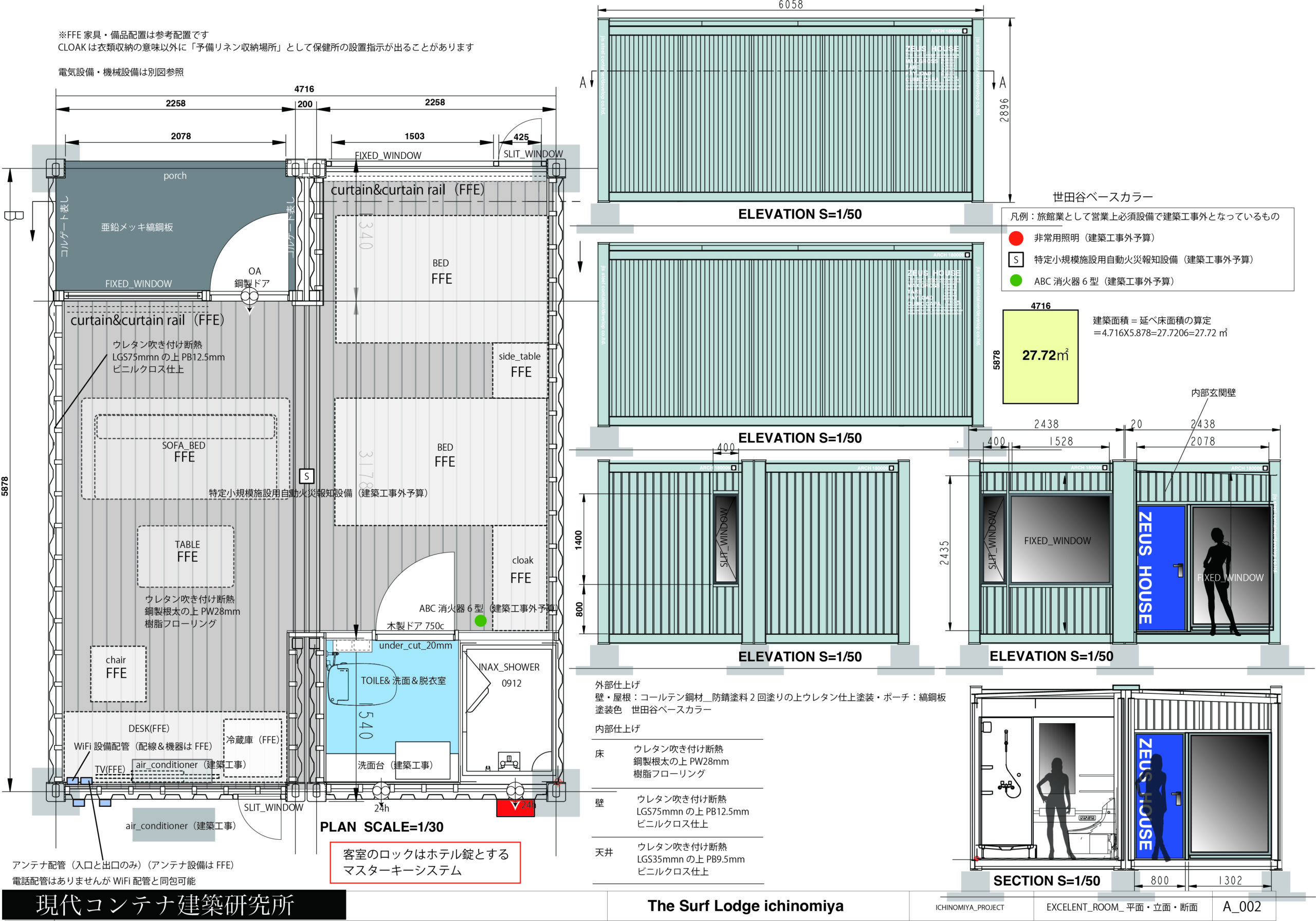
もくじ
■ 10坪(33㎡)が生み出す「ちょうど良さ」
コンテナハウスの広さを語るとき、10坪(33㎡)というサイズは一つの節目になる。
5坪は「ソロ暮らし」や「趣味の小屋」に最適だったが、10坪になると夫婦二人が無理なく暮らせるミニマルハウスへとスケールアップする。
しかも、これが「別荘」や「セカンドハウス」として考えると、必要十分な広さでありながら維持コストも抑えられる。
「大きすぎず、小さすぎない」──これが10坪という絶妙なバランスだ。
■ レイアウトの可能性:ワンルーム+ロフト or 2K
10坪のコンテナハウスで多いのは二つのタイプだ。
ワンルーム+ロフト
20フィートコンテナを横に2台並べる構成で、
ワンルームの大空間を確保しながら、ロフトベッドや収納を立体的に使う。
吹き抜け感のあるリビングは、夫婦二人の暮らしに心地よい広がりを生む。
2K(寝室+小さなリビング)
リビングと寝室を分け、最小限ながら「区切りのある暮らし」を可能にする。
例えば、平日はワークスペースとして、週末は完全な休養の場として使い分けられる。
どちらも「ミニマルだが不便ではない」という現代的な住まい方を支える。
10坪の暮らしは、余白の少ない生活でありながら「豊かさ」を育む。
家の中には必要なものしか置けない。
だからこそ、選び取ったモノと時間に囲まれる暮らしになる。
夫婦で小さなキッチンに立ち、
朝は森の匂いとともにコーヒーを淹れる。
夜は折りたたみテーブルを広げてワインを飲み、
「今日はどんな一日だった?」と語らう。
そんな風景こそが、10坪の家が持つ「濃密な暮らし」だ。
■ 別荘・セカンドハウス需要
別荘としての10坪は「現実的な夢」を叶えてくれる。
広大な別荘地に大きな家を構えるのではなく、
必要十分な空間を確保しつつ、自然と向き合うための小さな拠点を持つ。
都市の暮らしと行き来する「二拠点生活」
週末にだけ森や海辺で過ごす「リトリート」
災害時には避難拠点になる「セーフティーハウス」
10坪のコンテナハウスは、贅沢すぎず、しかし豊かに「もうひとつの居場所」を持ちたい人に最適なサイズだ。
■ 実用的なセカンドハウスサイズ
セカンドハウスを考えるとき、維持費や固定資産税の負担は大きな課題になる。
しかし10坪のコンテナハウスなら、建築用新造コンテナによる堅牢なつくりと、ミニマルなサイズ感により初期投資・維持コストともに現実的に収まる。
しかもユニット化されているため、将来必要になれば拡張も可能。
「まず10坪から」始めて、ライフスタイルの変化に合わせて増築する──
これもまたコンテナハウスならではの強みだ。
■ 体験としての10坪
森のコンテナハウス研究所では、実際にこの10坪サイズを**「見る・触れる・泊まる」**ことができる。
小さな玄関を開け、コンパクトながら居心地のいいリビングに腰を下ろし、
夜にはロフトに上がって寝袋にくるまる。
たった一晩で、「10坪という空間がどれだけ濃密な暮らしを生むのか」が実感できる。
見学だけではわからない“時間の流れ”を体験できることこそ、最大の魅力だ。
■ エピローグ:小さな家、大きな未来
10坪(33㎡)のコンテナハウスは、小さい。
けれどその小ささは「不自由」ではなく「自由」への入り口だ。
モノを選び、暮らしを選び、未来を選ぶ。
そうして見えてくるのは、夫婦二人で過ごす濃密な時間であり、
もうひとつの拠点を持つことで得られる安心感だ。
夢は大きな豪邸にだけ宿るのではない。
夢は、10坪という小さな箱の中にも、
きっと豊かに息づいている。
記事の監修者

大屋和彦
九州大学 芸術工学部卒 芸術工学士
早稲田大学芸術学校 建築都市設計科中退。
建築コンサルタント、アートディレクター、アーティスト、デザイナー。