失敗しない
建築パートナーの選び方
満足できる
コンテナハウスを建てるために。
あなたの理想に近いコンテナハウスを建てるためには、信頼できる建築パートナーを選ぶことが最も重要です。
しかし残念なことに、中には悪質な業者も存在し、満足のいくサービスを提供しない場合もございます。
お客様がトラブルを避け、後悔しないコンテナハウスを手に入れるために、
建築業者を選ぶ際に確認すべき3つのポイントをご紹介します。

 建築パートナーの選び方
建築パートナーの選び方
POINT 01
違法建築に注意!
建築基準法を遵守し、
建物の資産価値を守る。
国土交通省の通達によりますと、コンテナハウスは「建築物」とみなされます。
「建築物」は建築基準法を守る必要があります。
建築基準法は国民の資産や町を安心安全に保つために考えられた法律です。
その基準に合わないコンテナハウスは建築基準法違反とみなされ、改善を求められたり、著しい違反の場合は撤去命令を受けることがあります。
コンプライアンスは現代の常識です!
コンテナハウスで建築基準法をクリアするには、信頼できる建築会社のパートナーを選び、トラブルに巻き込まれないように注意しましょう。

コンテナハウスを頼むなら「コンプライアンス」
と「力量証明」をクリアしている会社に!
コンテナハウスは、デザインやコストだけでなく、法的に安心できるかどうかがとても重要です。建築基準法や各種規制をクリアしていないと、せっかく建てても「違法建築」になってしまうリスクがあるのです。
さらに、その会社に“力量”があるかどうか──つまり、正しい資格や認定を持ち、きちんと施工できる実力を証明できるかどうかも欠かせないチェックポイントです。
ここでは、コンテナハウスを発注する前に必ず押さえておきたい「コンプライアンスと力量証明の確認項目」を整理してみましょう。
1. 製造・加工環境 ― 工場の認定と品質保証 まずは製造段階の信頼性。
- ●工場認定:建築基準法に適合した工場か。国土交通省の大臣認定や性能評価を取得しているかどうか。
あるいは国際的な基準を示すLloyd's Register Rulesなどもクリアしていると安心です。 - ●品質保証:鋼材の厚み、溶接、防錆処理などが基準通りか。これらの基準を作っているかなどもポイントですね。 さらに第三者機関のチェック(溶接部のチェック)を受けているかどうかなどは2階以上の建物などの場合大きなポイントです。
工場自体が公的に認められていることは、そのまま「品質の裏付け」になります。
2. 施工会社の登録と資格 ― 法的に工事できる会社か
次に、施工を請け負う会社の法的な資格。
- ●建設業許可:特に「建築一式工事」の許可を持っているかどうか。内装工事業のみとか、水道工事業だけではなく「建築一式工事」でなくてはいけません。
- ●建築士事務所登録:確認申請を出す設計や構造計算を行う場合には必須。
- ●資格者の配置:現場管理には施工管理技士、設計や確認申請には建築士が関わっているか。
ここが弱いと、建物そのものは完成しても「合法建築」とは認められないケースが出てきます。 これらは当然クリアさせています。
3. 行政手続き ― 建築確認から検査済証まで
どんなに小さなコンテナハウスでも、住宅や店舗として使うなら「建築物」として扱われます。
- ●建築確認申請:用途地域や容積率、耐火基準などをクリアしているか。
- ●消防法対応:特にカフェや宿泊施設では避難経路や防火設備が必須。
- ●検査済証の取得:完成後に検査を受けて「検査済証」が交付されているかどうか。これがなければ売却や融資が難しくなります。
行政との手続きをしっかり踏んでいるかどうかが、合法かつ資産価値のある建物かを分けるのです。
最後の、完了検査を受けないと言う建設業者がいます。建築確認申請をし、済証をもらったから大丈夫と、完了検査を受けず検査済証をもらわない業者がいます。ここは気をつけましょう。
4. 発注前に必ず確認すべきチェックリスト
最後に、契約や発注をする前に確認しておきたい項目をリスト化しました。
- 施工会社 「建設業許可証」を提示できるか
- 設計会社 「建築士事務所登録証」を持っているか
- 工場 国交省認定・性能評価を受けているか
- 実績 過去に建築確認申請や検査済証を取得した事例があるか
まとめ
コンテナハウスは自由度が高く、魅力的な建築スタイルです。けれども、法的なコンプライアンスと製造・施工の力量証明をクリアしている会社に
依頼しないと、後々トラブルや資産価値の低下につながります。
「安いから」「デザインが良いから」だけで選ばず、 資格・認定・実績を持つ会社かどうか!ここを確かめるのが、安心して建てられる第一歩です。
建築基準法を遵守するには

JIS鋼材を使用した建築用コンテナを使用しているか?
輸送用コンテナはJIS鋼材ではありません。
日本の建築物の要件を満たしましょう。

建築確認申請を通しているか?
完成後の完了検査を受けているか?
行政の許認可をうけ建築し、完成後に検査を受ける必要があります。
完了検査を受けているかどうかでその後の建築物としての価値が違います。
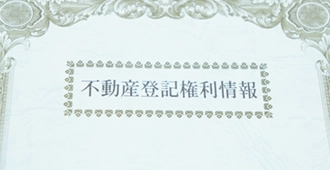
建築物として登記ができるのか?
血統書のある建築物としてきちんと登記をし、資産として管理しましょう。
POINT 02 価格で選ぶと危険!
「安い」の言葉は落とし穴。
コンテナハウスは安いという言葉は、中古のコンテナを改造する際によく聞く様に思います。中古コンテナそのものは確かに、どこでどんな使われ方をし、どのような年数が建っているかもわからないものは、それなりに安く手に入るかも知れません。
しかし、それを建物として整備する為には「基礎工事」「本体の断熱工事」「電気設備工事」「給排水設備工事」「開口部の工事(窓・扉)」「空調換気工事」「内装仕上げ工事」「照明器具の取り付け」など、普通の建物と同じように各種工事が必要になり、コンテナは「構造体」として使われます。
その構造体が「中古」というだけで、窓やドア部分を開けるという加工や、その開口部の補強工事をする必要があります。このような手間を考えると、何か安くなる部分があったら教えて欲しい。というくらい「安くなる要素」が見当たりません。
なぜ「安くなる」のか、なぜ安いと言っているのか、よく考えてみましょう。購入価格が「安い」のは、概ね自分で内装工事をするような「セルフビルド(自力建設)」の場合だけの様に思えます。安い理由をしっかり確かめてみましょう。

コンテナハウスを作るときにかかる主な費用
![]()
土地代
![]()
コンテナ本体代
![]()
基礎工事費用
![]()
運搬・設置費用
![]()
断熱費用
![]()
電気設備費用
![]()
給排水設備費用
![]()
空調換気
設備費用
![]()
住宅設備費用
![]()
内装仕上げ費用
![]()
IT系設備費用
![]()
設計監理費用
意匠・構造計算
当社の設計したコンテナハウスは、設計の内容とグレードによりますが、一般的な平均値は100万/坪程度です。
木造よりは少々高めで、重量鉄骨の在来工法よりは少し安く、RCよりは概ね安いというようなイメージになります。
それぞれの工事や設備費用について適正な価格で見積もりをとってくれる建築パートナーに依頼しましょう。
POINT 03
パートナー選びの要!
施工事例のココを見る!
コンテナハウスの業者の中には、主に販売のみを行う会社や、当社のように設計から施工までを行う会社があります。
ひと口にコンテナハウスの業者といっても会社によって、
できること、また得意なジャンルが違います。
そのため、満足のいくコンテナハウスを作るには、自分の実現したいコンテナハウスの事例があるのかを確認しておく必要があります。

施工事例はここをチェック!

コンテナハウスの施工実績数
輸送用コンテナはJIS鋼材ではありません。
日本の建築物の要件を満たしましょう。

得意ジャンル・得意分野
行政の許認可をうけ建築し、完成後に検査を受ける必要があります。
完了検査を受けているかどうかでその後の建築物としての価値が違います。

設備対応できる範囲
血統書のある建築物としてきちんと登記をし、資産として管理しましょう。
